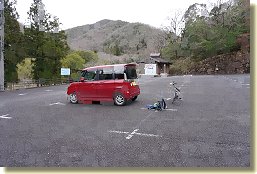その時、ここは北から南へのコースも行けるな、いずれ行ってみよう、と考えていて、今日トライするわけです。
高速道路の尾道道を北尾道インターで下りる。御調に向かわず府中の方向へ進んで行く。
御調川沿いに進んで芦田川と合流する。芦田川を遡上していく。芦田湖=八田原ダムの下流まで遡上するのですよ。
ダム堰堤下が河佐峡、そこの駐車場に車を停めようとしているのですよ。この案内がそうだからね。見落とさないようにね。
駐車場の地面が斜めになっている。サイドブレーキを必ず引いて下さい、とある。歩いていて目が回るのだよ。水平とかけ離れていて、体が異常を感じるのだよ。
さて、自転車で走り出す。
県道56号線と立体交差する。県道に合流して、福塩線河佐駅がある。列車のすれ違い駅のようで、プラットホームが対面ではなく、互いににずれている。
プラットホームの島と島を結ぶ踏切はなく、それぞれが出入口を持っている。
変なのはね、ここは久佐町なんですよ、河佐町はもっと下流にある。よその土地で、河佐駅だの、河佐峡だの、名前の付け方がおかしいよ。それはね。
明治のはじめ、合併して河佐村ができたんですよ。それで、河佐駅・河佐峡と命名したけど、昭和の高度成長期、合併して河佐村が消えてしまった。大字名で呼ぶようになって、名前が浮いてしまったのです。
次の踏切、石垣踏切を渡る。このあたりは久佐の集落、集落の途中で自転車を下りて押して歩くことになる。
集落を外れたあたりから諸毛町の範囲に入る。諸毛町は広いのだが山林ばっかりで、集落は山の上にしかないのだよね。
この谷には砂防ダムは何か所かあると思うよ、わたしの目に見えたのは一か所だけだった。木が茂っていて谷を見下ろせないものね。
民家が見えてきた。たんぼが見えてきた。北諸毛圃場整備の石碑がある。ふぅん、諸毛を北諸毛・南諸毛と分けて呼ぶんだな。
峠が見えている。あそこまで行けば下り坂になるんだぞ。もうちょっと押して歩こう。
きっつぅ、峠の下はかなりの傾斜、自転車を押して歩いても堪える。登り切った、峠の上は民家が立ち並んで、四本の道がある。当然、直進する道を進むべきだろう。
はい、出ました。県道383号線に合流した。横に郵便局がある。ちょうど局員が外に出てきた。
ちょっと聞きたいんですが、ここは諸毛で郵便局は諸田とありますよね、田の字はどこから引いてきたのですか。
昔はね、諸田という地名だったのですよ。今では諸田という地名は消えましたが、名残に残っているのですよ。
なになに、地名が消えただと、これは異様なことを聞いた。調べてみねばなるまいて。
明治の初めのころ、全国で旧来の村々を束ねてひとつの村にする運動があった。それで諸田村が誕生した。諸毛村の諸と大山田・下山田の田を足して、諸田村にしたんだろうね。
明治・大正・昭和の戦後・高度成長期まで諸田村は続いた。
1955年(昭和30年)西の大山田・下山田・千堂が分離して合併、御調町が発足した。人口の多い中核部分が分離したので、残った諸毛・小国は翌年府中市に編入された。
67年間も、諸田村は存続したんだよ。郵便局、旧小学校に諸田の名前は残っている。小学校は廃校になった。郵便局も採算が取れているかはどうかと思うし、廃止も近いと思うよ。
郵便局から進むと、南諸毛の集落が見渡せる。このへんから南のたんぼが始まるのだよ。
かなり谷の流域のたんぼは広い。突然たんぼは途絶える。この先は谷が急峻でたんぼを拓く余地がないのだ。
弥生時代、たんぼは山の中腹から始まった。平野は水害が怖くてなかなか定住できなったのだそうな。今なら山の中腹にたんぼがあるのは異様だが、昔々はこれが正常なのだよ。
急な下りが始まる。ブレーキを握り締め、谷側に寄らずに山側に身を寄せて下りていく。
途中の道幅が広くなったところで弁当を広げる。タイヤに触ってみるとホカホカと暖かい。ブレーキの摩擦熱なんだね。
まだまだ下り道は続く。やっと山道が開けて市街地が見渡せるところまで出てきた。
ここが福塩線下川辺駅、無人駅、単線駅だなぁ。この先で国道486号線に合流する。
芦田川を渡る橋が大渡橋、しまったなぁ、どう読むのかを確認し損ねた。おおわたりばし、おおわたしばし、だいとばし、どう読むのだろうなぁ。
ここの信号交差点名が父石、父石町の範囲はけっこう広いのですよ。
ここから県道24号線を遡上して行く。芦田川と山に挟まれて、道幅が狭い。自転車の横をバス・トラックが追い越していく。ここは耐えて進むしかない。
芦田川が折れ曲がって反転するほどの急カーブに出てきた。芦田川って平たく言えば、西から東に流れているんですよ。時々グイッと南に流路を変える。ここがそうだし、福山の神辺でも南に向きを変える。
もうちょっと進めば落合三差路、県道24号線は直進して上下に向かう。わたしは川沿いに進んで県道56号線をたどる。
もう少し進むとトンネルがある、久佐トンネル、自転車乗りはトンネルを好かない、トンネルを避けて旧道を行く。トンネルの左側に道があるのだよ。
旧道を進むと、福塩線が野崎山トンネルを出て旧道と並行して走っている。
県道56号線に戻る。走っていくうち、石垣踏切に到着。河佐駅まで戻ってくる。そのまま進んで、河佐峡へと案内がある。立体交差を潜って進んで行く。
河佐峡の駐車場の看板が見えている。さぁ、帰ったぞ。
|
標高 |
隣との標高差 |
出発からの距離 |
隣との距離差 |
区間の勾配 |
| 河佐峡駐車場 |
268m |
|
|
|
---- |
| 石垣踏切 |
143m |
10m |
1187m |
1187m |
10/1187=-0.9% |
| 諸毛の峠 |
362m |
219m |
3969m |
2782m |
219/2782=+7.9% |
| 父石交差点 |
43m |
319m |
9635m |
5666m |
319/5666=-5.6% |
| 落合三差路 |
123m |
80m |
16964m |
7329m |
80/7319=+1.1% |
| 河佐峡駐車場 |
153m |
30m |
20168m |
3204m |
30/3204=+0.9% |
別ページ、轍のページに、断面図=プロフィールマップがあります。傾斜の凹凸はそっちのほうがより感覚的に理解できると思います。
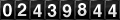
![]()

 詳細地図、地図上のどこで撮った写真なのか解ります
詳細地図、地図上のどこで撮った写真なのか解ります 轍 でも軌跡を示しています、高低を示す断面図も表示できます
轍 でも軌跡を示しています、高低を示す断面図も表示できます